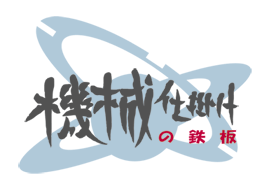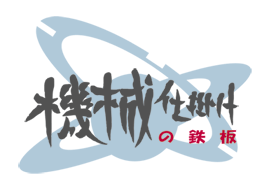リガウ島の奥地トマエ火山のさらに奥
今は詩人に身をやつしている太陽神にして神々の父は、例によって冥府にお邪魔していた。
「本当に邪魔だ。帰れ」と弟の死の王が言うのも聴かずにずかずかと中に入り込み、ちゃっかりと来客用のダイニングテーブルに腰をおちつけ、さらに冥府の裏番長である大法官に「お気遣いなく、お茶だけで結構です」と謙虚そうに、その実かなりずうずうしく要求したりしていた。
こうなったらだれも止められるものはいない。
さすがは神々の頂点に立つものである。
死の王は諦観し、自分も兄である太陽神の向かい側に座る。
「帰れ」と、ほとんど習慣で言ったものの、絶対にそれが聞き入れられることはないと言うことは何百回、何千回と同じことを繰り返してきた経験からよくわかっている。が、だからといって、気持ちよく迎え入れるのは、できない相談だった。
今も戦い続ける弟や永遠の苦痛の中で生きている妹に申し訳が立たない。
故に、兄である太陽神に対してこのような態度に出ざるを得ないのだろう。と
大法官ユリウスは主の心中をそのように考察している。
少なくとも、光の神を嫌っているわけではないことは、いろいろ理由をつけて訪れる光の神をなんやかや言いながらも相手にしていること、そして、珍しく(これでも)饒舌に談話していることからわかる。
間違いなく、死の王は「妹はともかく、愚兄や愚弟のことなど心底どうでもいい」と否定するだろうが。
「どうぞ」
大法官ユリウスは二柱の神の前にお茶を置いていく。
「いや、本当に気をつかわせてしまって・・」と笑顔で一応すまなさそうに、しかし心底ではそう思ってなさそう口調で言った。
「おや、それは何です」
光の神はユリウスが小皿にとりわけたお菓子に気づいた。
「見てのとおりのただのチョコレートだ」
ユリウスに代わって、死の王が若干あわてて答えた。
と、言っても骸骨の仮面に隠れて表情は伺いしれない。
「ええ、それは見ればわかります。でも、珍しいですね」
土地柄のせいか、普段、ここで出されるお茶請けといえば、大福、練り切り、羊羹、団子、せんべいと言ったリガウの菓子がほとんどだった。
「しかも、あまり「ただの」とはいえないようですよ?」
光の神は出されたチョコレートを手にとって眺めながら言った。
その形はハート。しかもご丁寧に赤やピンクのチョコレートでなんだかよくわからない花の絵や「LOVE」という文字だのが描かれていた。
間違いなく、店で買った既製品ではなく、手作りのものであろう。それもだいぶての込んだ一品だ。
正直いって、この骸骨面を見につけ、厳格な性格であると知られる死の王がこれを食べている図を想像するのは、空恐ろしくもある。
「およそあなたに似つかわしくありませんね。一体どうしたのですか?」
「・・・・」
死の王は答えない。面の奥の表情はわからないがおそらく相当困っているのだろう。
「先日、アムト殿が持ってこられたのですよ。」
黙り込んだ主に代わってユリウスが答え、そしてあきれたように付け加えた。
「例によって今年も」
それをうけて、太陽神は意地の悪そうな笑みを浮かべ、納得したようにいった。
「ああ、そういえば、昨日はアムトの祝祭日でしたね。」
アムトの日。
どこかの世界で2月14日である飛竜月4日は赤い月アムトが誕生した日として定められている。
もちろんほかの神にもそういった祝祭日はもうけられており太陽神は夏至・帝虎月11日(6月21日)、闇の女神は冬至・魔鳳月14日(12月25日)、死の王は昇鳳月2日(11月2日)、海神は土狼月20日(7月20日)、森神は地狼月4日(5月4日)がそれにあたる。
当然ながら、神の代に現在の人間の定めた暦があるわけもなく、後付で定めたものであるが、それは神を信仰する人間にとって些細なことだ。
ただ、神をあがめる為の口実があればよいのだ。
それはさておき、
アムトの日、最初は愛の女神であり赤い月の女神に感謝をささげる日であったが、どこで、どうゆがめられたのか、今ではすっかり「好きな人にお菓子をあげる日」になってしまった。
お菓子の中でも特に見栄えが良く高価なチョコレートがその対象になってしまったのは、間違いなく、菓子屋が仕組んだ卑劣な罠であろう。
「そんな人間の世界の習慣など私は知らぬわ。あの赤い月が義理チョコだから特に深い意味はないと言いながら、勝手においていったのだ。」
死の王は憮然としながら言った。
「ふーん、義理チョコねえ・・」
太陽神は人の悪そうな笑みを絶やさずに、ハートの形をしたチョコレートをもてあそんでいた。
「それにしてはずいぶん手の込んだ品ですねー♪」
「おぬしも貰ったであろう。アムトはこれからみんなに配ってくるといっていたぞ。」
「・・・・」
死の王の言葉に光の神はふてくされ、黙りこくってしまった。
思ったことをそのまま口にしただけで他意はなかったが、図らずも痛烈なカウンターパンチを食らわせたようだった。
確かに光の神は娘からチョコレートを貰った。それは確かだが、量販店でどこでも手に入り、安価な点が売りの板チョコ一枚貰っただけだった。
「・・・父への愛は10金にも満たないと・・・そう言いたいのでしょうかね・・・あの馬鹿娘は・・」
そういいながら、太陽神は大げさにため息をつきながら嘆いた。
その様子を見ていた死の王はしばらくほうっておくことにした。
声をかけようがなかったからだ。
歩く騒音の異名をもつ太陽神が沈黙した事によって、いつもの静寂がおとずれたが。それも5分ほどしか持たなかった。
嘆き悲しむという行為に飽きた太陽神がまた別の興味の対象を見出したからだ。
「冥府に花とはこれはまた珍しいですね。」
太陽神の目線は死の王が普段仕事で仕様している机の上。
そこに置かれた素焼きの鉢に植えられた赤い花にあった。
冥府にも花はある。三途の川の両岸には地上で見かけるありとあらゆる種類の花がある。
正確にはかつて花だったものの魂というべきか。
だが、そこにあるのは生命溢れる本物の花だった。
太陽神はまるで、懐かしいものを見るようにしばし、その花を眺めた。
そして視線を赤い花に向けながら弟に尋ねた。
「あれも、ウチの娘が置いていったのですか?」
「・・・・」
死の王は沈黙で返した。
どうせ何を言ったところで、それは肯定としかとられない事を分かっていた。それなら、無駄な労力は使わないに越した事はない。
太陽神は弟の様子を楽しんでいたが、少しばかり腹立たしくもあった。
最後に生まれたが故に一番可愛がって育てた娘なのに、その父である自分には何故量産品の板チョコだけなのかと、考えれば考えるほど口惜しくてならなかった。
光の神は腹立ち紛れに、自分の分のチョコレートだけでなく、弟の分まで両手に鷲づかみにし一気口の放り込んだ。
あまりの早業に死の王は何事かと呆気に取られた。
事態が飲み込めたのは、兄が「うん、これでいい。気がすみました」と満面の笑みを浮かべながら某冒険者の口調で言いはなち、それを全部嚥下した時だった。
「エロール、貴様!」
死の王は自分でも理由は良く判らなかったが、珍しく心底腹をたて、太陽神に掴みかかった。
「いいえ、私は悪くありませんよ、悪いのは貴方です」
太陽神は誰一人として納得しそうも無い意味不明な弁解をし、弟をもぎ離そうとする。
食べものの恨みは恐ろしいのだ。
「・・・・・」
後ろのほうで一部始終を見物していた大法官ユリウスはやれやれと呆れながらため息をついた。
神々とはなんとくだらない存在なのだろうと、神は神という肩書だけで崇め奉られすぎである・・・・・と思った。
放っておきたいところだが、下手をしたら第2次邪神戦争が勃発しかねないので、そうするわけにも行くまい。
神々とはまったく質の悪い存在だ。とユリウスは何千回、何万回とくりかえした愚痴を心の中だけで呟く。
「ああ、薔薇といえば・・・」
と、かなり唐突に切り出したのはそんな葛藤の末だった。
2柱の神が動きを止め怪訝な顔でユリウスの方に注目した。
その様子にユリウスはとりあえずほっとし、そして、かまわず先を続けた。
「アムトの日に贈り物をする際に、一緒に赤い薔薇を添える事が多いと聞きますが、あれには何か意味があるのですかな?」
「私が知る訳なかろう」
死の王は即答したが、それに対し
「だれも貴方にそんな事期待していません」
と、兄と大法官の双方に同時に突っ込まれた。
「・・・・」
死の王はふてくされて、湯のみに残ったお茶をがぶ飲みした。
「赤い薔薇の花にはね、」
そんな弟の様子を横目で見ながら太陽神は語りだした。
「貴方を愛します、という意味があるのですよ。」
と、此処まで言ってから、弟の死の王の方を見たが、骸骨の面の奥の表情はわからない。いっそその面をもぎ取ってしまいたい衝動にかられたが、今は止めておく事にした。
「だから、普通は異性の人には薔薇は贈らないことになっているのです。
誤解されてしまいますからね」
「・・・・」
死の王は相変わらず黙ったままだった。
ユリウスも自分から話題を振ったものの、反応にこまり、結局あたりさわりのない相槌を打っただけだった。
「なるほど・・・そんな意味が・・」
微妙な気まずい沈黙が流れた。
太陽神は場の雰囲気を察したのか、愛用のツインネックのギターを手にとりながらこう切り出した。
「・・・実は、これには由来があるのです。」
「聞きたいですか?」
否といったところで、勝手に歌い出すであろう事は明白なので、死の王とユリウスは何も言わなかった。
それに、少々気になるのも事実。
そんな二人の心中を察してか、太陽神はかまわずギターの弦を爪弾く。
「薔薇の花、今は愛の神アムトの花と言われていますが、元々は大地の神であり、大地に属する者全ての母であるニーサのものでした・・」
光の神ははるか過去に思いを馳せながら謳う。
それははるかな昔、まだ創造神の代であった頃、太陽が大地に出会ったときの話だった。
それはまだ、マルディアス創世の頃。
エロールの子と呼ばれる種族はこの世界には存在しなかった。
その頃の人類は創造神マルダーと、その妻であり半身であるサイヴァによって生み出され、海の生命は海神オキナスによりうみだされ、地に生きる動物は愛の女神イシナスによって生み出され、大地と豊穣の女神ニーサは大地の草木すべてを生み出したといわれている。
今はドライランドと呼ばれるその土地は、古き神代の頃は、緑したたる豊穣な大地であった。
創造神とその妻子は、その豊穣なる大地を睥睨する位置に建つ、現在ではオールドキャッスルと呼ばる場所を居としていた。
現在は神々の父と呼ばれるエロールは最初から父であったわけではなく、創造神とその半身であるサイヴァの息子であり、当時は最も若い神であった。
「エロールは何処?」
神々の母なるサイヴァは息子の姿を探していた。
「さあ、先ほどまであちらに」
そう答えるのは法の女神メチスだ。その答えは城に大騒動をもたらした。
そんな様子を当の太陽神エロールは城の外に立つ巨木の上から笑いながら眺めていた。
そして、暫らくその様子を堪能した後、城の外に広がる森に姿を消した。
当時、エロールは人間で言えば10歳ぐらいである。
世の中の全てに興味がある好奇心旺盛な年頃である。
とても城の中の狭い空間だけで満足できるはずもなく、そうやって隙をみては外に飛び出していった。
城の中に居ては世界を知ることは出来ない。
この性癖は1000年たっても直るどころか年々酷くなる一方なのだが、それはまた別の話だ。
その森は常緑樹と広葉樹が適度な間隔で立っている、その葉の隙間からは暖かな日が差し込み、森の緑に様々なトーンを与えていた。
その樹木の下栄えには色とりどりの花が生えており、木陰からあらゆる種類の小動物が顔をのぞており、そして頭上では常に小鳥が音楽を奏でていた。
この森は生命に溢れていた。
「こんにちは」
エロールは行く先々で現れる小さな友達に挨拶をしながら、森の奥へ入っていった。
ここに来るのはもう何度目か自分にもわからなかった。
そのたびに前とは異なる場所へと足を運ぶ。
エロールはこの森が好きだった。
もし、楽園というところが存在するのなら、この場所こそがそうなのではないだろうか。
楽園とは意外とすぐ近くに存在するものなのだろう。
そんな事を思いながら、歩をすすめていた時の事だった。
「?」
森の中に異変を察知した。
風が運んできたのは歌であった。
それに導かれるように、一つの場所へ鳥たちは飛び立ち、動物達は駆け抜けていく。
そして、その音色は光をも引き寄せた。
エロールは、その発生源を探し求め、その音だけを便りにまだ見たことのない森の深部へと向かう。
一体歌っているのは誰だろう?その期待の交じった甘いような不安なような疑問だけが太陽神の心を充たしていた。
突如として明るい緑の迷宮は途切れ、光溢れる空間が目前に広がった。
「・・・!」
突然溢れた光の矢に一瞬視力をうしなった。
いや、その光はその小さな神から発せられたのかもしれない。
その驚きとともに。
そこは、赤、ピンク、黄、青、紫、その他形容できない様々な色の花々が咲き乱れていた。
そして、先ほどまでかすかにしか聞こえなかった歌が今度は明瞭に耳に届いた。
少し物悲しくすこし明るい旋律で、やや、アルトの落ち着いた歌声だった。
歌の内容は要約すると
もし、私が風になれたら、愛する人の元に行きたい。(※1)
というようなものだった。
エロールは秘密の花園の中に佇む人物をみとめた。
光神の位置からちょうど後姿しかみえなかったので顔は判別できなかったが、
大地と同じ色の髪をもつ女性である事がわかった。
その周囲には歌声に酔ったかのように青い色の鳥が何羽か戯れていた。
それは未来の神々の王の目にはとても幻想的でそして美しい光景に写った。
綺麗すぎて、触れたら消えてしまう幻のように思われた。
故にそれ以上近づけずに、その場所でしばしの間みとれていた。
(夢をみているのだろうか?)
夢であったら、まだ冷めないでほしかった。だが
それでも、確かめずにはいられず、思い切って声に出して呼び止めた。
「あの」
ばさ〜!!
エロールが一歩踏み出した時、鳥たちは一斉に飛び立っていった。
それによって、背後に人がいることを悟ったその女性は振り返った。
「誰?」
その時、未来の神々の父とその女性はお互いに、その存在を認めた。
視線が交わったその一瞬、何故か時間が止まったように感じた。

「・・・あ、すみません。」
先に言葉を発したのはエロールのほうだった。
そして、帽子をとっていつものように笑顔で挨拶をした。
「私はエロールといいます。」
「エロール・・・」
その女性は、最初の驚きからは醒めたようだが、今度はまた別のことでおどろいたようだった。
「・・創造神マルダー様とサイヴァ様の・・・」
自分に言い聞かせるようにそう呟いてから、エロール似向かって微笑みかけ、そしてドレスの裾をつまんで優雅に挨拶をした。
「初にお目にかかります。私はニーサと申します。どうぞ先のご無礼をお許しください。エロール様」
「いいえ!謝るのは私のほうです!」
エロールはその態度の大いにあわてた。確かに常から創造神とその妻の子であると言う理由から神々からは大仰に傅かれるが、正直言って、いつまでたっても慣れない。
むしろ、そうされるとむず痒い気分になる。
偉くて強いのは父と母であって、自分はまだ子供であり何の力もない、という事実を思い知らされる。
「驚かせてしまって申し訳ありません。あまりにも綺麗だったので」
エロールの言葉にニーサは嬉しそうにわらった。
「有難うございます。この花達も喜ぶ事でしょう」
本当は花ではなかったのだが、しかし本当のことをいうのも照れくさいのでやめた。
それに花が美しいと感じたのはウソではない。
「その花は貴方が育てたのですか?ニーサ」
「いいえ。花は自分の力で咲くのです。私はただ見守っていただけ・・」
そう答えながらニーサはてじかにあった大輪の赤い花をそっと撫でた
「花も、草木も、鳥も森にすむ生き物も、神々が介入することがなくとも、ただ一生懸命生きています、その姿は美しい・・・そう思うのです」
「ええ、そうですね。でも彼らは大地という母がいるからこそ、安心できるのではないでしょうか?」
ニーサは少し驚いたようにエロールを見つめた。
エロールは気まずそうに笑っていった。
「ニーサは大地を司る優しい女神だと、母が言っていたのを思い出しました。」
「ええ、そう、皆はそう言いますが、でも私はただ大地と共に存在しているだけです」
ニーサは戸惑ったように、そう言い、そして天を仰ぎ見ながら呟いた。
「生き物は太陽の光がなくては育ちません。エロール様、ここに咲いている花も貴方がいるから元気に生きる事ができるのですよ。私はいつも貴方に感謝しております」
「そ、そんな、ニーサ」
面と向かってそう言う割れて、この頃はまだそれほど図太い神経をもっていなかった光神は面食らった。答えに窮して、視線をさまよわせた。
そして、ニーサが手を触れた赤い花が目に入ったとき、生来の好奇心が鎌首をもたげ、唐突に質問した。
「その花、なんと言う花なんですか?」
「え?ああこの花は薔薇といいます。この花はとても香りが良くて香水の原料になるのですよ。そして、その花びらは薬にもなるのです」
「へえ?そうなんですか?どんな効果があるんですか?」
好奇心の塊となったエロールに苦笑しながら、説明書を読むようによどみなく答えた。
「バラで精製したオイルは火傷を鎮め、傷口を消毒する効果があります。その花びらを煎じたお茶は風邪や胃の痛みに効果があります。そして、その香りは精神を落ち着かせます。そしてそれだけの効能がありながら副作用がもっとも少ないと言われています。」
「すごい!万能な花なんですね」
エロールもまた大げさに感想を言うと、ニーサはなんとなく嬉しくなり、少し砕けたようすで
「エロール様、バラの花言葉、知っていますか?」
「花言葉?」
「いつか、貴方が誰かを愛したとき、その方に赤い薔薇の花を贈ると良いでしょう」
「へえ、そういう意味があるんですか。」
「でも、赤でもが少し黒味がかった濃い赤になると、全く違う意味になるので気をつけてくださいね(※2)」
そのように、エロールとニーサはしばし歓談していたが、やがて日が西に傾いてきた。
「そろそろ戻らなくては・・」
エロールは残念そうにそう告げた。
「ええ。それが良いと思います。サイヴァさまも貴方の身を案ておられる事でしょう。」
ニーサの言葉にエロールは忘れて居た事を思い出した。そういえば、抜け出してきたのだった。
城は今ごろ大騒ぎだろう。
「・・・そうですね。とても名残おしいですが、また会えますよね」
ニーサは小さな太陽神にむかって微笑みながら答えた
「ええ、私はいつでもここに居りますから。いつでも遊びにいらしてください」
「では、また来ます。」
エロールは嬉しそうに答えた。そして、一つみごとをした。
「その時はニーサ、私の事はエロールと呼んで下さいますか?」
「まあ、それは・・」
ニーサはその申し出に戸惑った。がエロールの次の言葉で思い直した。
「私は貴方対等でありたいのです。貴方の友達になりたい。」
「・・わかりました。たった今から私と貴方は友達ですね。エロール」
「とても、嬉しいです。」エロールは破顔した。
その瞬間、世界に光が溢れたような気がしたが、それは多分光神の心模様であろう。
エロールは心底名残惜しそうに。この花園から立ち去ろうと踵をかえした。
「それではまた会いましょう」
「お待ちください、エロールさ・・エロール、コレを持っていって下さい。」
エロールを呼び止めて差し出した掌に乗っていたのは小さな種であった。
「これは、この薔薇の種です。お近づきのしるしに、どうぞお持ちください」
「ありがとうございます。
・・・赤い薔薇が咲いたら貴方に贈りましょう」
「楽しみにしていますわ。」
光神の言葉は大人になったら忘れてしまう類の子供の戯言であろう。
と思ったが、その気持ちはうれしかった。
「と、まあこんな具合です」
神々の父は、今までかき鳴らしていたギターを隣の椅子に置いた。
そして、弟である死の王と大法官に尋ねた。
「私の歌はいかがでしたか?」
死の王は湯のみをテーブルに置きながら、答える
「よく出来た作り話だな」
「酷いですね。全て事実ですよ」
太陽神は真意のわからぬ微笑で答えた。
「では、それはおそらくお前の願望か妄想であろう」
死の王には、目の前の老獪な兄に純粋無垢な子供時代が会った事も信じられなかったし、いつも愚兄を尻に強いている天界最強の大地母神が、太陽神に対してそのような態度で接する事は想像すらできなかた。
勿論それは声に出さなかったが、太陽神は弟が言わんとすることを察し、遠い目をしながら付け加えた。
「まあ、人間、長く生きていると変わる事もありますよ。」
そして、弟に反撃した。
「貴方だって、昔は手のつけられない・・」
「そうだな。そういうことにしておいてやるかた余計な事を言うな」
死の王は口調にかすかに焦燥の色を帯びながら言った。
そんな兄弟神を横目で見ながら大法官の心の中には、太陽神への「人間じゃないだろう」という突っ込みよりも、主が慌てて否定するほどの過去への疑問が残った。
だが、それもどうでもいい事であった。何があったとしても所詮は過去の出来事だ。
「で、そのあと、その薔薇をニーサに渡す事は出来たのか?」
死の王はなんだかんだ言いつつも、兄の話の後日談が気になったので、聞いてみた。
「ええ。ですが、それはずっと後の事でした。」
光神は、弟にそう答え、そしてしばらく黙り込んだ。その顔にはいつも浮かべている人を食ったような微笑はなかった。
死の王はその理由が気になったが、太陽神のただならぬ様子にその質問を口に出すのを躊躇った。
それに、その様子でその後何があったのか、判りすぎるほどに分かってしまった。
その記憶は痛みを伴わずには思い出せないものである事も良く判っていた。
去っていく光神を見送りながら、ニーサは満ち足りた気持ちで一人微笑みながら、光神との絆となった薔薇の花弁に触れようとした。
「あら」
だが、それは触れるか触れないかの瞬間に突風が吹き、薔薇の花はあっという間にばらばらにに散って
しまった。
ふと、空を見るとつい先ほどまであんなに良い気候だったはずなのに、灰色の雲に覆われていた。
そして、再び視線を花園に戻した。
「!」
大地に散ったその深紅の花びらはまるで血ように見えた。
大地の流した血のように。
創造神マルダーの妻であり半身であるサイヴァが神々に反旗を翻したのはこの一年後の事であった。
|