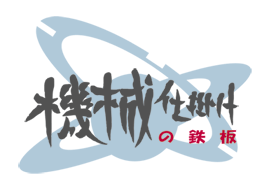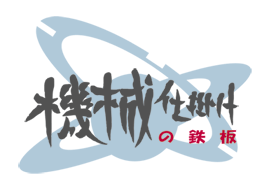飛竜月4日(どこかの世界では2月14日にあたる)
その日はアムトの日であるため、赤い月だけが夜空を照らしていた。
リガウ島。
ジェルトン郊外の山地から草原の彼方にトマエ火山の頂きが見える。
あの活火山の下には、魂の集まる場所がある。
肉体を捨て魂だけの存在となったものが行くところである。
それはつまり死を迎えると言う事である。
ゆえにそこは死と生の境界であると思われていた。
そこは冥府と呼ばれ、そこを支配する神は死の王として畏怖されていた。
人は死を恐れ、それが不吉な者であるかのように言う。
だが、生も死も魂の循環という一つの環の中において違う側面にしか過ぎない。
そのことを正しく知り、伝える者はいない。
かつて、この島には冥府の王を祭る神殿があり、その神殿の最高神官が王となり治めていた王国があった。
だが、その王国が滅んでもう何百年になるのか。
バファル帝国はこの王国自体を邪教と恐れ、弾圧し、王族に連なる血筋の者と神殿に関わる者を全て処刑し、この地に保管されていた書物を全て焼いてしまった。
いずれにしても、死と生、魂の輪廻を司る神を祭る一族は消え、精神的な支えを失ったリガウ島はバファルの圧倒的な力に屈した。
そして、血の融和政策により時ともにに帝国に同化していった。
最後に残った王族の血も帝室に取り込まれた。
だが、王国は滅んでも人々の心の中に其の信仰はまだ生きている。
生活の中のちょっとした習慣の中に、此処で生み出される工芸品の文様の中に、
この地の力が人々に信仰の火を灯すのか?
いずれにしても、この地の人々は死の神を畏れながらも敬う事を心の奥で忘れていなかった。
この山地にはかつて王宮だった建物が残っている。
王宮の敷地は大きく二つに分かれていた。
一つはゲクウと呼ばれる王族達の住む宮殿。
もう一つはナイクウと呼ばれる神を祭る社。
そして、それを守護するように周囲を覆う深い森は鎮守の森と言われている。
もちろん、全てがそっくりそのまま残っているわけではない。
王国が帝国に滅ぼされたとき、王宮は焼き捨てられた。
残ったわずかな建物も、手かつての壮麗さはなくあちこちの塗装は剥げ落ちており、わびさびといった趣を呈している。
それでも、手入れはされているようで、建物のかやぶきの屋根はまだつい最近葺かれたものである事が見て取れる。
リガウ王朝の事を記した者は全て喪失したが、人々の伝承の中にその記憶は残っている。
ジェルトンの人々はこの遺跡が何のために立てられた建築物かもわからないが、自国の文化遺産として手厚く保護している。
そして、その王宮の内宮にあたる敷地には木造の、シンメイ造りと言われる高床式の、素朴だが壮麗な建物がある。
リガウ独特の建物で、ほかの地域では見られないつくりのものだが、間違いなく神を祭る神殿である事は、そこに残された燭台や、鏡、祈祷書、祭壇などの神事用具から判別できる。
神殿である内宮は、帝国軍も完全に破壊するのを躊躇ったものと思われる。
玉垣に囲まれ、入口にはトリイと呼ばれる朱に塗られたの門があり、其の左手には手水舎と呼ばれる清めの場がある。そして、そこから神殿に伸びている大きな道は参道なのだろう。
参道は玉砂利が敷き詰められており、その両脇には崩れかけた石灯籠が等間隔に設置されており、炎が揺らめいている。
だれが、点灯するのかは定かではないが、その灯りが耐えたことはない。
だが、その炎はあまりにも儚く、今にも消え入りそうで、かえって周囲の森が作り出す闇を強調するかのようだ。
その幽玄ともいえる灯りの中、白いローブを着た人物は突如あらわれた。
もし、誰かがこの場に居合わせたら、恐怖のあまり逃げ出すであろうと思われた。
其の人物が骸骨にしか見えない面をつけ、ミイラを髣髴とさせるように肌が見えぬ程腕に包帯を何重にもまきつけているのもまた、恐怖を増幅させる。
だが、幸いだれもここにはいなかった。
それはその男にとっても幸いであった。むしろ其の男が包帯に覆われた腕に抱えている意識を失った少年にとって。
もし、誰かが見ていたら明日にはジェルトン中の噂になってしまうことだろう。
自分は構わないが、この子供にとって好奇の目でさらされるのはよいこととは思われなかった。
白いローブの人物は参道の先にある内宮ではなく、そこから分かたれた横道にはいり、その先につづく外宮へと向っていった。
外宮へ続く参道があったと思われる入口にもまた内宮にあるものと同じ形のトリイがあった。
だが、こちらのトリイは元は朱色だったのであろうが、ほとんど元の色がわからないぐらいに剥げ落ちていた。
神を祭る内宮はそれゆえに帝国軍も手出しが出来ず、王国民の信仰のよりどころを破壊することによる弊害を時の大法官に説かれ、王国を支配したのちもその管理を島民に任せたのだが、宮殿である外宮は完全に破壊され、ここに立ち入る事を厳重に禁じた。
王国の記憶を風化させるためであった。
そして、それはもくろみ通りになった。
禁じた帝国軍のほうも島民のほうも何故この場所が立ち入り禁止とされているのかわからなくなった。
そして、今となっては何処からたったのか「もののけが出る」とか「たたりがある」とかいう風評がまことしやかに信じられており、恐れてだれも近づかなくなった。
その上、それを信じた島民はその何者かを厳重に封印するかのように外宮入口の鳥居を注連縄と守り札を幾重にも張り巡らした。普通の人間なら其の異様な様子を見ただけで恐怖を覚えることであろう。
故に外宮は破壊されたときのまま打ち捨てられた。
外宮への道も鎮守の森の木々が侵食し、苔に覆われ完全に失われてしまった。
ただ、鳥居だけがその奥になにかあるらしい事を暗示している。
「下らぬ事だ。」
白のローブの人物―死の王は何の躊躇もなく、注連縄と何重にも施された結界の札をものともせず、森の地面を覆うシダ化の植物を無造作にかきわけ、鳥居をくぐっていっき、その奥にある、かつて外宮であった場所へ向った。
何百年もここに立ち入ったものはないので、道など判別できるはずもないが、この人物はまるで道がわかるかのように迷いもなく進んでいった。
外宮へ至る道の途中、死の王は足をとめた。そして、静かに口を開いた。
「何の用だ。」
死の王が呼ばわった先には何も存在しなかった。
だが、突如として、天の赤い月から一条の光がさしたかと思うと其の赤い光は、一人の女性の姿をとり始めた。
誰かと問うまでもなく正体はわかりきっていた。死の王は露骨に嫌そうな顔をした。が、面を装着しているのでそれは本人にしか知りえない事だ。
とはいえ、気配でそれはさっせられるであろう。
相手はそれを気付かなかったか、もしくは気付いていて気付かないフリをしたか、おそらく後者であろうが、艶やかな微笑を浮かべてまっすぐに死の王のもとにやってきた。
今、天にあって地上を照らしている月と同じ色の髪を持つ女性はこの死の王が最も苦手な人物でもあった。
故に、自分から聞いておいて、相手が答える間も与えず、声を荒げはしなかったが、切りつけるように言い放った。
「用がないなら天に帰れ。今はお主と下らぬ議論をしている暇はない。」
人間であれば、怖れをなして逃げ出した事である。だが、人間ではない赤い髪の人物は全く動じた気配はなく、何も聞かなかった事にし、死の王に近づいた。
正しくは、その腕に抱えられ、意識を失っている少年に、と言うべきか。
赤を纏った人物は、その白い手を少年に伸ばした。
「上からずっと見ていたわ。その子があの人の子供ね」
死の王は何も反応を示さなかったので、更に続けた。
「あの、今は人間となって世界をさまよっているかわいそうなあの、闇の・・」
「何故、お主が知っている?」
今度は、紅い月の言葉に反応し、そして明らかに不機嫌そうな声でそれを遮った。
兄である神々の父は確かこう言っていた「私は、このことをほかの誰にも、得に妻には知られたくないのです。」と。また、「そのことを知れば、余計な心配と疑惑を引き起こす事になるでしょう。」
紅い月は一瞬、目を丸くしたが、その質問の真意を悟り、おかしそうに声を上げて笑いながら答えた。「ふふ、女性の感を舐めてもらっては困るわ。
父様にも困ったものね。よりによってニーサに隠し立てできるとでも思ったのかしら」
「・・・・」
女神と対象的に死の王は無言だった。が、表には出さないが、内心かなり動揺し、そして警戒した。
常々感じている事だが、奴は神々の父という仰々しい肩書きを名乗っているくせに、妻にだけは頭が上がらないらしい。最強の神である大地が知っているという事は他の神にも知れ渡っていることだろう。
それを見透かしたか、紅い月は付け加えた。
「ああ、でも安心して、私たちはそのその子には危害を加えるつもりはないから。それに男達は気づいていないわ。勿論、バラすつもりもないしね。」
「では、何故、ここに来た?」
帰れと言外に語る死の王に対し、月の女神は上目遣いに見上げて歌うように言ってのけた。
「ふふ、ただの好奇心。」
その言葉を聞くや否や、外宮にむかって歩き始めたその背に向って声が追いかける。
「それに、その子怪我しているわね。ほうっておいたら死んじゃうよ」
それはそのとおりだった。この子供の傷を癒すのは、もともと、術よりも力技のほうを得意とする自分では手に余るだろうと思っていた。
そして、月には癒しの力がある。
だから彼女が追ってきても今度は拒絶しなかった。 |