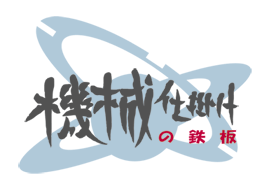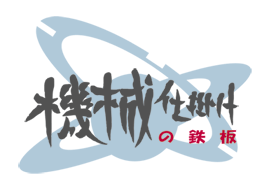何一つ、形をとどめていないと思われた広大な廃墟の中に一つだけ、なんとか人がすめそうな家屋があった。
王宮と同じく堅牢な作りではあったが、一つの装飾もなく実用本位な質素な建物である。
王族の住まいではなく、その使用人、それも王族に直接仕える侍従や女官ではなく、最下層の下働きの住まいであったのだろうと思われる。
月の女神はその建物を見ていて気づいた事がある。
建造物の基礎となるはたしかに古いが、何度も、修復した跡があり、少なくとも今すぐに崩れ落ちる心配はなかった。そして、建物の中には生活するのに必要な道具が置かれていた。それらは使おうと思ったらすぐに使えるような程度に手入れされていた。
間違いなく、誰かが住んでいて、そして、わざわざこんな所に住もうとする者は一人を置いていないであろう。
赤い月は、今まで抱えていた怪我をした子供を手当てしようと床に横たえ、その傍らに腰をおろした死の王に尋ねた。
「父様が言っていたわ、死の王は大法官と口論する度に冥府を抜け出ししばらく帰ってこないって。その時にここに非難しているのね?」
死の王は答えない。別に答える必要は感じなかったからだ。月の女神もそれは期待していなかったので、かまわずに続ける。
「それにしても、何で王宮ではなく、こんな場所に?」
死の王は、少年から傷口を手当てするのに邪魔になる衣服を慎重に剥ぐ手を休めずに言った。
「住むのに、豪華な装飾や広い場所など必要はない」
「ふうん。そう、でも貴方の治めている場所は質素とは程遠いようだけど」
死の王の治める冥府は無駄に広く、装飾過多としかいいようがない、針のような繊細なゴシック調の装飾に覆われている。
「あれは、前にあそこを治めていた者の趣味だ。」
別段表情もかえず、答えた死の王の言葉に紅い月は何かひっかかる物があったが、それは問い詰めてはいけない様な気がしたので、会話を切った。
赤い月は今まで、障子越しに月明かりに紅く染まった廃墟を眺めていたが、視線を横たわった子供に移し、そして死の王の隣に腰をおろす。
今はとりあえず、この子供の傷を治さねばならない。
その顔色は、行灯のゆらめくオレンジ色の灯りにてらされても、なお蒼白であった。
月の女神は、あらためてその顔を観察し、そしてこういった。
「よく似ているわね・・・・」
その言葉に死の王は何も反応せず黙々と作業を続ける。
「この子は知っているのかしら?自分の親の事・・」
赤い月はここまで言いかけたが、血に染まった衣裳を取り除いたの少年を見て絶句した。
そして、怒ったように傍らの死の王に尋ねる。
「ちょっと、一体どうしのコレ」
ついさっき、少年が幼馴染の女の子をアンデッドから庇ったときに受けた傷は左肩のあたりであった。思っていたよりも大きな傷であった。アンデッドの爪が、あと少し下方まで振り下ろされていたら、心臓に達し、絶命していたであろうと思われた。
おそらく、すぐに手当てはしたのだろうが、それはあまり意味をなしていなかったようだ。血は止まらずに流れ続けたままだ。
死の王が急いでいたのは、紅い月と係わり合いになりたくないからばかりではなく、この子供がどれほど危険な状況にあるか分かっていたからだと悟った。興味本位でこの子供に近づき、そしてそのことでからかった事を反省した。
だが、月の女神が驚愕したのはその傷に対してではなかった。
少年の小さな身体にあった傷はそれだけではなかったからだ。命にかかわるような大きな傷ではなかったが、腕や背中、わき腹のあたり、今まで衣服に隠されていて見えなかったが、その体のあちこちに裂傷や痣があった。
ごく最近つけられたと思われる傷もあり、見ているだけで痛々しい。
「一体、誰が、そんな事を?」
怒りからか、悲しみからか、声を震わせながら赤の月は尋ねた。
死の王はそれには答えずに、今まで赤い月のほうに顔をむけ、頼んだ。滅多に誰かを当てにすることのない、死の王にしては珍しい事だ。
「私は癒しの術をもたぬ、おぬしの力でこの傷をふさいでくれぬか?」
「え、ええそうね」
紅い月は動揺してはいたが、すぐに、自らの役割を思い出したように、術を施す為に意識を集中した。
その周囲に今、天にある月と同じ紅い光が集まる。その光を右手に集約させ、そして、それを少年のいまだに血を流し続ける傷口にあてがった。
束の間、その光が部屋中に広がったかとおもうと、ゆっくりと消えていった。
その頃には肩口の傷はすっかり塞がり、うっすらと痕がのこるだけとなった。
その光景を見ていた、死の王は少しだけ感心した。
蒼白で苦しそうな表情を浮かべていたその子供は今は、幾分血色が戻り安らかな寝息を立てていた。おそらく明日にはごく普通に目覚めるだろう。
「感謝する」
珍しく、本当に珍しい事だが、死の王は赤い月の女神に謝礼した。月の女神はその様子に少し驚き、そして得意気に笑いかけたが、すぐに視線を先ほど癒した子供に移し、そして再び硬い表情にもどった。
肩の傷は癒えた。だが、無数に負った小さな傷はまだ残ったままだ。
そして、先ほどは肩の傷に気をとられていて、気づかなかったが、癒えたばかりの傷口の下あたり、左の胸のあたりにとても古い傷痕がある事に気づいた。古いが深い傷だった。それは、さっき癒した傷のようにモンスターの爪でつけられた物ではなく、鋭利な刃物で突いたかのような深い傷跡だった。まるで、心臓を突き刺そうとしたかのような。
赤い月は一つの事実に思い至ったが、それはあまり愉快とはいえないことだった。
でも、一体誰が?
おそらく隣の人物は知っているのだろうが、口に出して問うのがためらわれた。
真実を知るのが怖かった。
自分達はとんでもない思い違いをしていたのかもしれない。
死の王は使い物にならなくなった血塗れた衣服ではなく、何処からもってきたのか、別の服で、その体を覆った。まるで、その傷をこれ以上晒すのを避けるかのように。
しばしの間、この空間は沈黙に支配された。何か言わなくてはと思うが、適切な言葉は何一つ思い浮かばなかった。
だが、安らかに眠る目の前の子供を見ているうちに紅い女神の心に怒りが湧いてきた。
「一体誰が・・・」
そして憤りに声を震わせながら、誰に言うでもなくそう呟いた。
傷は明らかに人によって傷つけられたものだ。同じ人間のそれも子供にたいして何故このような酷いことができるのか。
「心に闇を持たぬ人間など存在せぬ」
赤い月は唐突に言う死の王に顔を向けた。死の王は寝入っている少年から目を離さずに、続ける。
「普通は折り合いをつけていくものだ。だが、何かのきかっけで、心に巣食う闇が暴発し、表出する事がある。」
「そのきかっけがこの子だと言うの?」
怖れながら尋ねた紅い月の女神に死の王はただ、頷いただけで答え、話を続けた。
「そして、それを向けるのはまずそのきっかけを作ったものであろうな。そして、その対象となる者が自分より弱者であったら・・・」
「でも、この子はまだ自分の中にある闇に気づいていないはず。」
死の王の言葉を遮るように言う月の女神に目を向けたが、すぐに視線を元にもどし、そして寝ている子供の髪に手を触れた。それは灰色だった。そこと目の色だけが今は人間となった妹と異なっていた。いや、かつて目にした時は確か妹と同じ色の髪をもっていたはずだった。その時の事を思い出し、沈痛な表情を浮かべた。
「自覚だないだけで、その力は確実にこの子供の中にあるのだ。」
だからたちが悪い。気付いていないということは、その体に宿る他者に影響を与えるほど強大な闇の力が流出するのを抑える事が出来ないということだ。
純粋な闇に触れてなお、自分の心にある闇を抑えられる人間などそうはいない。
そう考えて月の女神は戦慄を覚えた。
もし、この少年がずっと人の世界にいたら、どうなるか。父たる光の神が心配した事とは異なる事態に陥るのではないかと初めて思い至った。
「いずれ人の手によって殺されるかも知れぬと思っていた」
表情も変えずに、口にしたその言葉に反射的に振り返った。
何かを言おうと思ったが、何もいえなかった。それはきっと事実であろう。
「だが、神が人間に関わるわけには行かぬ。だから、エロールの依頼は好都合だった」
神々の父自らの頼みであれば、誰も意義を唱えるものはいないだろう。
神と人との間には越えてはならない一線がある。特に人間の生死の循環を司る神である自分はそれに対して、関わることを自ら禁じていた。
どんな死に方をしようと、それはその人間の定めであり、そして、死は全ての終わりではなく、次の生へ移行する一つの段階でしかないのだから。
死の王が人の生死に関わるということは魂の正常なる流れを妨げる事になり、そして死の王はその事をよく理解していた。
だから、人間となった妹が新たな生命を宿した時も、何も手出しをしなかった。
妹の子供であるといってもただの人間である少年がどういう人生を歩もうとそれもまた定めだと割り切ろうとしていた。
むしろ、次の輪廻では少なくとも今よりはマシな人生を歩む事が出来るだろうと考えたが、その存在は小さな刺のようにかすかに心に痛みをもたらした。
だが、光の神の願いはその子供に接触する行動にたいして絶好の口実だった。
「そう。それなら良かった。貴方ならきっとこの子を護る事が出来るわね。」
月女神は死の王の葛藤を知り、そして、何かに満足したように呟いた。
「貴方にしか出来ない・・」
月女神はもう一度そう言うと、今度は死の王に向き、そっと頬に手を触れた。
死の王は微動だにせずにただ受け入れていた。
「少しだけ、妬けるけど」
軽く笑いながら、そう付け加えると、そのまま立ち上がり、そして
「帰るわ。その子が目覚める前に」
そして、現れた時と同じように一条の光となり、そして忽然と消えた。
まるで、今までそこに存在していたのが嘘であったかのように跡形もなく。
父である太陽のように存在自体が騒がしい月が去って、辺りは本来あるべき静寂に満ち溢れる。死の王はただ、ため息と共に言葉を吐き出した。
「一体あれは何をしに来たんだ?」
再び、眠る少年に視線をむけ、そして思った。
少なくとも、これの命をつなぎとめてくれた事には感謝しよう、と |